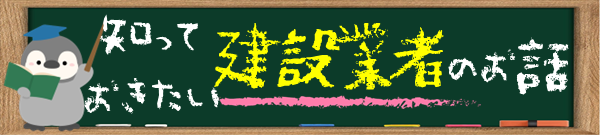京都府の建設業許可申請手引きの許可の要件の欄の一つ目に次のように書かれています。
・適正な経営体制があること
では、単純に適正な経営体制とは何でしょうか?
それは
「ある役員等が」(ある経営者者)が
「ある経験」を有していること
が必要です。
経営体制と言葉は難しいですが原則として役員に一人は建設業の経営経験者が就いてほしいということです。
原則ですから、それが緩和し補ったような例外もあります。
それで見ていきます。
「ある役員等が」
「ある役員等が」とぼやかしたのは役員等についても細かく書かれているからです。
そして役員等であっても「常勤」であることが必要です。
少しわかりやすく表にまとめてみました。
| 「常勤」 | + | 法人の場合 |
持分会社(合名・合資・合同会社)…「業務を執行する社員」 株式会社(指名委員会設置会社以外)…「取締役」 株式会社(指名委員会設置会社)…「執行役」 法人格のある各種組合等…「理事」 「取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等」 |
| 個人事業主の場合 |
本人 その支配人 |
※役員には監査役、会計参与、幹事及び事務局長は入りません。
まず「常勤」について引用していきます。
「常勤である者」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者をいいます。したがって、他社において常勤役員等・常勤役員等を直接に補佐する者・営業所の専任技術者となっている者は「常勤である者」には該当しません。また、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き、「常勤である者」には該当しません。
つまり簡単に言うと「片手間ではやらないで」ということでしょう。
次に上記の表の用語を解説していきたいと思います。
「法人」…法務局に登記された団体です。
「個人事業主」…明確に定義はありませんが法人ではなく税務署に開業届を提出している者ぐらいの意味でしょう。
「持分会社」「株式会社」…持分会社とは株式会社と対になる会社の種類。こういった名前の会社はなく「合名会社・合資会社・合同会社」をまとめて示した名称である。ここでは詳しくは解説しないが株式会社では「所有と経営が分離されている」(出資者つまりお金を出す者と業務執行つまり会社で指揮を執る者が原則、別」が、持分会社では「所有と経営が原則分離されておらず」株式会社とは逆である。
「委員会設置会社」…大規模の会社が指名委員会、監査委員会、報酬委員会、そして執行役を設置する。ここでも詳細は解説しないが、委員会を設置しないの会社の取締役が業務を執行するように委員会設置会社では執行役が業務を執行する。
「登記された支配人」…簡単に言うと個人事業主がある程度の規模を持ち始めると営業所を複数持ち始めたます。その時にその各営業所により代表者を置くことがありますが、そのとき「支店長」など会社内の決定事項だけでは社外の人間には信用に置けない場合もあります。その場合、法務局に登記することによって社外の人間にも支店における権限を証明することが可能です。そして法的にも裁判上内外における権限を与えています。
「取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等」…取締役会等に出席や発言することはないが、役員等から直接的に権限を渡される。取締役に近い限りなく近いもの。
「ある経験」
では「ある経験」とはなにか?
簡単に言うと
「建設業の」経営経験をした者ですか?ということです。
具体的にどういった経験をしている必要であるかを見ていきましょう。
常勤役員等に経験者が一人いればいれば要件を満たす場合
次の表の中で①~③のだれか一人、原則として本店に常勤役員としていれば経営業務管理責任者の要件を満たします。
| 建設業に関して | ①経営業務の管理責任者として5年以上の経営経験を有すること |
| ②権限ある執行役員等として5年以上の経営経験を有すること | |
| ③経営業務の管理責任者に準ずる地位で、6年以上経営業務を補佐した経験(以下「補佐経験」という)を有すること |
用語解説から入ります。
経営業務の管理責任者…
営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業のについて総合的に管理しを経験をいいます。具体的には、法人であれば業務を執行する社員、取締役、執行役、法人格のある各種組合の理事等、個人事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位似合って、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。
法人においても個人においても建設業許可をもっての経営管理の経験している必要はありません。つまり、許可がない建設業の経営経験も有効です。
また、日本国内の経験が原則となりますが、海外での建設業の経営管理経験は例外的に認められる場合があります。
国土交通大事から、経営業務の管理責任者と『同等以上の能力を有する』旨の認定を受ける「国土交通大臣認定」です。「国土交通大臣認定」を受けるのは日本人(海外企業での経営経験)、外国人を問われません。
ちなみに他社での経験も有効です。
権限ある執行役員等…
取締役会の決議により特定の事業部門に関し権限委譲を受け、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。つまりは、取締役会設置会社に限られことになります。
ほぼほぼ取締役に近い存在であるが取締役会などでの発言権はないといった感じのポジションです。たとえば、取締役でない者が他業種を営む法人で建設部門の代表者として経験している感じです。
建設業許可の申請において上記の「経営業務の管理者」にくらべて、商業登記簿等の謄本が存在しないため確認書面等での立証は大変です。
また場合によっては行政との折衝も必要となります。
こちらも他社での経験でも有効です。
経営業務の管理に準ずる地位…
業務を執行する社員、取締役、執行役もしくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者で建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験した者となります。
他社での経験も認められます。
常勤役員等に一人+その直接補佐する者が一人以上いる場合
| 常勤役員等としてどちらかの要件を持つものが必要 |
①以下(a)~(c)のいずれかの経験(建設業役員として5年間は含むもの) (a)役員等または役員等に次ぐ職制上の地位における、建設業に関する5年以上の財務管理の業務経験 (b)役員等または役員等に次ぐ職制上の地位における、建設業に関する5年以上の労務管理の業務経験 (c)役員等または役員等に次ぐ職制上の地位における、建設業に関する5年以上の業務運営の経験 |
|
②5年以上の役員経験(建設業の役員等の経験2年以上を必ず含むこと)※3年は建設業以外の役員経験でも構わない |
※他社での経験も可
こちらが常勤役員等の一人が持たなければならないの要件ですが、上記の一人だけでいい場合にくらべて要件が緩和されています。
そのかわり常勤役員等以外にプラスその直接補佐する者を付けてやってくれとの趣旨です。
ではさっそく直接補佐する者を見てみましょう。
|
直接補佐する者 |
(a)役員等または役員等に次ぐ職制上の地位における、建設業に関する5年以上の財務管理の業務経験 |
| (b)役員等または役員等に次ぐ職制上の地位における、建設業に関する5年以上の労務管理の業務経験 | |
| (c)役員等または役員等に次ぐ職制上の地位における、建設業に関する5年以上の業務運営の経験 |
※他社での経験は不可。自社経験のみ可。
まず用語解説します。
直接補佐する者…
組織体形状および実態上常勤役員等との間に他のものを介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいいます。
財務管理の経験…
建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験
労務管理の経験…
社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験
業務運営の経験…
会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験をいいます。
そして直接補佐する者は次のよう取り扱われます。
※(a)~(c)のすべての経験が存在することが必要です。ですが、一人が複数の業務経験有している場合は複数の役割を兼務できます。
※また業務経験を積んだ期間の換算は期間を重複できますので、一年で財務管理経験と労務管理経験の各一年づつ積むことも可能です。
※少し細かい話ですが、平成28年からの『とび・土工工事業」にかかる経営業務の管理者責任者としての経験(又は経営業務を補佐した経験)は「解体工事業」にかかる経営業務の管理責任者としての経験とみなされれます。以前は「解体工事業」という業種がなく『とび・土工工事業』者が解体工事業を行っていたからです。
※経営経験には合法な経験しか算定されません。例えば、建設業の許可がない場合において請負代金の額が500万円超えて請け負った工事については経験数にはカウントされません。また解体工事業、電気工事業、浄化槽工事業(許可業種では、管工事に含まれます。)については請負金額の多寡を問わず登録が必要となるため登録以前のこれらの工事は経験数にはカウントされません。
まとめ
経営業務の管理責任者は建設業許可の取得についてはネックになる要件です。
また商業登記簿で証明できる確認書類ならいいのですが、商業登記に記録されない経験などは書面が複雑になります。
よく親子で承継する場合、役員等の経験年数が足りず許可を断念せざるを得ない場合も散見されます。
親子承継をお考えの方は会社であれば取締役の就任登記、個人事業主であれば支配人登記を早めにされるのがよろしいかと思います。