生業扶助とは
生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、次に掲げる事項の範囲内において行われます。ただし、これによって、その収入を増加させ、またその自立を助長することのできる見込みのある場合に限られます(生活保護法第17条)。
①生業(職業)に必要な資金、器具又は資料
②生業に必要な技能の修得
③就労のために必要なもの
生業扶助は、被保護者の稼働能力を引き出して、それを助長することにより自立をはかることを目的として行われます。生業扶助は、それによって、被保護者の収入を増加させ又はその自立を助長することのできる見込みのある場合に給付されます。
生業扶助の内容
生業扶助の内容は、3種類に分けられます。
①「生業に必要な資金、器具又は資料」(生業費)とは、生計の維持を目的とした小規模の事業を営むために必要な資金・器具・資料をいいます。この場合の資金も、金融機関による大規模な貸出金のようなものではなく、例えば、小さな商売を開始するのに必要な運転資金のようなものをいいます。
②「生業に必要な技能の修得」とは、生計の維持に役立つ生業に就くために必要な技術を修得させたり、公的資格を取得させたりすることをいいます。例えば、美容学校、洋裁学校その他の専門学校で技術を修得したり、保育士、介護福祉士、社旗福祉士その他の公的資格を取得する場合があります。
③「就労のために必要なもの」とは、就職の確定した被保護者が就職のために直接必要とする洋服類、靴その他の者の購入費用をいいます。
高等学校等修学費については、教育扶助ではなく生業扶助として給付されます。高等学校の卒業は就職に不可欠というべき状況になっていることから、生業に必要な技能の修得に必要なものとして生業扶助の対処とされています。小学校と中学校の修学費用は教育扶助の対象とされています。
生業扶助の方法は次の通りとされています(生活保護法第36条)。
①生業扶助は、
「金銭給付」
によって行います。
ただし、例がとして、
(a)これによることができない場合
(b)これによることが適当でない場合
(c)その他保護の目的を達するために必要がある場合
は、「現物給付」によって行うことができます。
※実務上では現物給付によるようです。
②現物給付のうち、就学のために必要な施設の共用及び生業に必要な技能の授与は、授産施設(障害者や高齢者など、働くことが困難な人に就労や生産活動の機会を提供する施設)若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設に委託して行うものとしています。
③生業扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付します。ただし、施設の供用又は技能の授与のために必要な金品は、授産施設(障害者や高齢者など、働くことが困難な人に就労や生産活動の機会を提供する施設)の長に対して交付することができます。
生業扶助の給付額の一般基準は次の通りになっています。
別表第7 生業扶助基準
※ 下記の表は更新される可能性があります。現行をお知りになりたい場合はお近くの社会福祉事務所にお尋ねください。
| 区分 | 基準額 | ||
| 生業費 | 47,000円以内 | ||
| 技能修得費 | 技能取得費(高等学校等就学費を除く。) | 87,000円以内 | |
| 高等学校等就学費 | 基本額(月額) | 5,300円 | |
| 教材費 | 正規の授業で使用する教材の購入または利用に必要な額 | ||
| 授業料 | 高等学校等が所在する都道府県の条例に定める都道府県立の高等学校における額以内の額 | ||
| 入学料 | 高等学校等が所在する都道府県の条例に定める都道府県立の高等学校等における類以内の額。ただし、市町右存立の高等学校等に通学する場合は、当該高等学校等が所在する市町村の条例に定める市町村立の高等学校等における額以内の額。 | ||
| 入学考査料 | 30,000円以内 | ||
| 通学のための交通費 | 通学に必要な最小限度の額 | ||
| 学習支援費 (年間上限減額) | 84,600円以内 | ||
| 就職支援費 | 33,000円以内 | ||
その他にも自動車運転免許の取得が雇用の条件となっている場合、専修学校その他の各種学校で技能を習得する場合、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座で公的資格を取得する場合には特別基準による生業扶助があります。
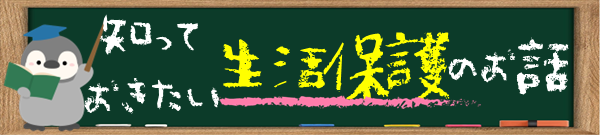
1-320x180.jpg)
2-320x180.jpg)
3-320x180.jpg)
4-320x180.jpg)
5-320x180.jpg)

3-160x90.jpg)