審査請求前置主義
行政庁(福祉事務所長その他の保護の実施機関)の申請拒否の処分に不服がある場合は、行政不服審査法による不服申立(審査請求)をすることができますが、不服申立とは別にその拒否処分の取消訴訟を提起することができます。
しかし、生活保護法第69条は、特例として「この法律の規定に基き保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消の訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない」と規定しています。この特例を「審査請求前置主義」といいます。
審査庁(知事)の裁決を経た後は、厚生労働大臣に対しての再審査請求をすることもできるし、原処分(当初の福祉事務所長その他の保護の実施機関の拒否処分)の取消訴訟を提起することもできます。
この両方を同時並行して行うことができます。処分の取消訴訟は当初の原処分の取り消しを求めるものであって、審査請求の裁決の取り消しを求めるものではありません。
以下、三つのパターンがある。
審査請求は不服申し立ての中でも簡易に手続きとなります。
とはいえ、法律実務に精通していない個人では申請書をつくるのは難易度が高く、時間がかかるのでなるだけ、弁護士又は行政書士に依頼されるの方がおすすめです。(生活保護の受給を受けられないと命にかかわることが多いため。)
次の取消訴訟は不服申し立ての中でもとても大変で難しいです。
弁護士に依頼すること一択で考えてもらうのがベストです。(本人訴訟等することが可能ですが法定さばきの良し悪しで敗訴してしまうのでここは迷わず弁護士さんに依頼してください。また、弁護士さんも専門がありますのでインターネット等を使って生活保護を扱われている方をお探しください。)
・審査請求のみ提起し取消訴訟はしない
・審査請求を申請した後、取消訴訟を提起する
・審査請求、取消訴訟を同時並行で行う。
処分の取消訴訟
処分の取消訴訟とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(これを行政処分といいます)の取消を求める行政事件訴訟法に規定する特別の訴訟をいいます(行政事件訴訟法3条2項)。
処分庁(例えば、福祉事務所長)の原処分(当初の拒否処分)事態の取消を求める訴訟なのです。
行政不服審査法の対象は、「行政庁の違法又は不当な処分」(法令に違反する処分又は保冷には違反しないが公益に反する処分)とされていますが(行政不服審査法1条1項)、取消訴訟の対象は、「違法な処分」に限られます。
行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分や裁決の相手方に対して次の事項を書面で教示する必要があります(行政事件訴訟法46条1項)
① その処分や裁決に係る取消訴訟の被告となる者
② その処分や裁決に係る取消訴訟の訴えの提起ができる期間
③ 法律にその処分についての審査請求の裁決を経た後でなければ処分の取消訴訟を提起することができない旨の定めがある場合は、その旨
日本の法律制度では、最終的に破産申請による裁判の確定を持たなければ問題は解決しないのですが、取消訴訟を提起し行政機関が敗訴した場合は最高裁判所まで争いますから、膨大な時間と費用を必要とすることになります。
従って、生活保護申請に対する拒否処分に対しては、費用のかからない審査請求をするとともに、拒否処分の理由を十分に検討して拒否処分理由に当たらない再度の保護申請をすることが大切です。
国家賠償請求訴訟の提起
自治体の福祉事務所の公務員にような「公権力の行使に当たる公務員」が、その職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた場合は、自治体が賠償する責任を負うこととされています(国家賠償法1条1項)。(簡単にいうと自治体といえども個人と同じく違法な行為を行えば賠償する義務を負います。)
例えば、福祉事務所の公務員が嘘の説明をして申請者を騙したり、申請者の生存権を侵害するような違法な処分をした場合又は申請者の名誉を棄損した場合には、国家賠償法により自治体を被告として損害賠償請求訴訟を提起することができます。
最高裁判例では、この場合に違法行為をした公務員を被告とすることはできないとされています。
保護申請に対する却下処分の取消訴訟と国家賠償請求訴訟とは性質が異なりますから、両方の訴訟を同時に提起することも可能です。
処分の取消訴訟に国家賠償請求訴訟も訴訟の手続は、取消訴訟の特例を除いて通常の民事訴訟と同じになります。
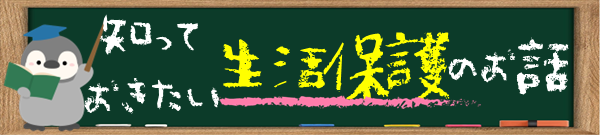
1-320x180.jpg)
2-320x180.jpg)
3-320x180.jpg)
4-320x180.jpg)
5-320x180.jpg)

5-160x90.jpg)
3-160x90.jpg)