生活保護の申請主義とその例外
生活保護法第7条は、
「保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる」
として申請主義の原則とその例外を規定しています。生活保護は申請主義を原則(自らが役所に報告)としていますから、生活保護申請書は、要保護者(保護を必要とする状態にある者)の居住地(実際に生活している場所)の自治体の福祉事務所長(保護の実施機関)宛に提出します。居住地を有しない場合や居住地が明らかでない場合(例えば、ホームレス状態の場合)は、現在地(現に所在している場所)の福祉事務所長あてに提出します。申請書の用紙や添付書類の用紙は、福祉事務所の窓口で無償で交付を受けられます。
生活保護の申請をすることができる者(申請権者)は、次の通りとされています。
①要保護者(保護を必要とする状態にあるもの)本人
②要保護者の扶養義務者
③その他の同居の親族
生活保護法での扶養義務者の範囲も民法の規定する範囲と変わらず次の通りです。
①夫婦間の扶養義務(生活保持義務)
②親権者の未成年者の子に対する扶養義務(生活保持義務)
③直系血族(例えば、父母、祖父母、子、孫)、兄弟姉妹の相互の扶養義務
④特別の事情のある場合の3親等内の親族(おじ、おばまでの親族)間の扶養義務
この④の3親等内の親族は、家庭裁判所の審判により、特別の事情があって扶養能力があると推測される場合に限られます(民法877条2項)。民法に定める扶養義務者の扶養は生活保護に優先して行われますが(生活保護法第4条2項)、扶養義務者の扶養が受けられないことは保護開始の要件ではありません。
保護の実施機関(福祉事務所長)は、保護の開始の決定に際して扶養義務を履行していないと認める扶養義務者に対して
(a)申請者の氏名
(b)申請のあった日
の通知をすることとしています。
しかし、一律に通知をするのではなく、保護の実施機関(福祉事務所長)が、次のいずれにも該当すると認めた場合に限られます(生活保護法施行規則2条)。
①扶養義務者に対して、費用の徴収を行う蓋然性が高いと認めた場合
②配偶者から法律に規定する暴力を受けている者でないと認めた場合
③通知により申請者の自立に重大な支障を及ぼす恐れがないと認めた場合
更に、保護の実施機関は、保護の決定や費用徴収等のため必要があると認める場合は、扶養義務者が扶養義務を履行せず、上記①②③のいずれにも該当する場合には、扶養義務者に報告を求めることができます。(生活保護法施行規則3条)
申請主義の例外として、要保護者が、急迫した状況にある場合には、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができるとしています(生活保護法第7条但書)職権(職務上の権限)による保護の開始について、生活保護法第25条1項は、「保護の実施期間は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもって保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない」としています。
民生委員や近隣住民のような申請権者でない者から要保護者の存在について福祉事務所に通報があった場合は、福祉事務所長は、要保護者に保護の申請を促したり、本人が申請をすることができない急迫した状況になる場合は、福祉事務所長の職権で保護を開始する必要があります。福祉事務所の公務員が必要な保護を怠り要保護者を餓死させたり衰弱死させた場合は、状況によっては保護責任者遺棄罪(刑法218条)の責任を問われる場合があります。
生活保護申請書の提出
生活保護申請に必要な用紙は福祉事務所で職員に相談すれば出してもらえると思います。また、職員が必要な用紙を交付しない場合(近年、水際作戦と称され福祉事務所が申請書面を交付しないことがあったりします。)は理由等を問い交付できない理由を書面化してもらうといいでしょう。(生活保護申請の相談にのる等は職員の職務です。)
どうしても、交付してもらえない場合は弁護士等の専門家に相談するとよいでしょう。
生活保護法第24条1項は、
「保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただし、当該申請を作成することができない特別の事情があるときは、この限りではない。
一 要保護者の氏名及び住所又は居所
二 申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係
三 保護を受けようとする理由
四 要保護者の資産および収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。)
五 その他の要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項」
生活保護は、世帯を単位として保護の要否や程度を定めることを原則としていますから、(世帯単位の原則)、保護を受けるよう保護者全員について記載する必要があります。(生活保護法第10条)
生活保護法第3条3項は、「保護の実施期間は、保護の開始の申請があったときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなけらばならない」とし、同法24条4項は、「前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。」としています。この決定の通知は、特別の理由のない限り申請のあった日から14日以内にする必要があります。(生活保護法第24条5項)。
いわゆる水際作戦として、福祉事務所の公務員が、その職権を乱用して、生活保護申請書用紙その他の必要な用紙を交付せずに申請者の権利の行使を妨害した場合は、公務員職権乱用罪(刑法193条)成立しますから、申請書その他の必要な用紙の交付を強く要求します。また、公務員が違法に必要な用紙を交付しなかった場合は、後日、国家賠償法によってその公務員の属する自治体を被告として国家賠償(損害賠償)請求訴訟を提起することもできます。
申請時期と保護開始時期
生活保護法第7条は、「保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする」として申請主義の原則を規定していますから、保護の対象となるのは、申請時点(申請書の福祉事務所長への到達時点)以後の扶助しか対象となりません。申請書の到達時点の前から保護を要する状態にあったとしても、申請書の到達時点以後しか保護の対象となりませんから、何を置いてもまず、生活保護申請書だけでも福祉事務所長あてに郵送で提出しておきます。(受領を拒否することはできません。)不足している書類があれば福祉事務所の担当者から連絡があります。しかし、必要な書類の提出が遅れた場合は福祉事務所長の決定の期限が延長される場合があります。
かつての生活保護申請の実務は、多くの自治体の福祉事務所で申請をしようとする者に対して公務員との「面接相談」を強制して申請書用紙の交付も拒否していたことも多く言われています。公務員のこの行為を「水際作戦」と称して多くの自治体で行われていたため、平成25年11月の生活保護法の改正法律案の審議に際して参議院厚生労働委員会は「生活保護法の位置を改正する法律案に対する付帯決議」として「いわゆる水際作戦はあってはならないことを、地方自治体に周知徹底すること」とした決議をしているのです。水際作戦によって申請書の用紙を交付せずに保護申請自体をさせなかったり、保護申請の時期を遅らせたり、保護開始の時期を遅らせたりしていたのです。担当公務員の判断で申請用紙の交付を拒否し申請をさせない場合は、保護申請に対する福祉事務所長の決定(行政処分)が受けられず、その決定に対する不服申立もできないこととなって申請者の権利を侵害することは明白です。
保護申請の処理期間
保護の実施機関(福祉事務所長)は、保護の開始の申請があった場合は、保護の要否、種類、程度及び方法を決定(行政処分といいます)し、申請者に対して書面で通知をする必要があります。(生活保護法第24条3項)この書面には決定の理由を記載する必要があります。(生活保護法第24条4項)
申請者に対する書面による通知は、申請のあった日(申請書が福祉事務所に到達した日)から14日以内にする必要がありますが、扶養義務者の資産や収入の状況の調査に日時を要する場合その他の特別な理由がある場合には30日間まで延長した場合は、その理由を申請者への通知文書に記載する必要があります(生活保護法第24条5項)。30日間まで延長した場合は、その理由を申請者への通知文書に記載する必要があります(生活保護法第24条6項)却下の決定がなされた場合は、不服申立(審査請求)をすることができますが、その審査の結論が出るのに時間がかかりますから、却下の理由を検討して再度の申請をすることが大切です。
何が言いたいかというと、社会福祉事務所を含む役所は時として書類を受け取ったまま審査せず長期間放置することもありました。(「申請の握り潰し」とも言ったりします。)そういったことがないように、いついつまでに申請者に通知することにしています。
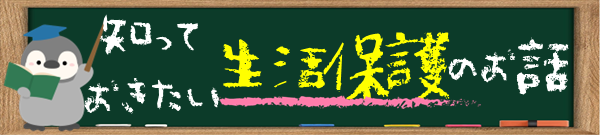
1-320x180.jpg)
2-320x180.jpg)
3-320x180.jpg)
4-320x180.jpg)
5-320x180.jpg)

1-160x90.jpg)
2-160x90.jpg)