面接相談
まず、最初に知っておいていただきたいことは生活保護法またその関連法令には生活保護申請を行うために面接相談を前提としなければならないという規定は存在しません。
但し、生活保護に限らず役所に書類を申請する場合は何らかコミュニケ―ションをとること(挨拶レベルものから相談レベルのものがあります)がほとんどです。 「水際作戦」といわれるものの一つにこのようなコミュニケーションを利用されたりもします。(※悪質な職員に限ります)あたかも面接相談が義務であるかのように仕向け(一般人にはわからない)申請をさせる前に相談という形をとるようにします。
そして、知らないことを利用して生活保護の申請を妨げるように仕向けるのです。
「若いうちは生活保護が受給できない。」「精神疾患では受給できない。」など様々です。
平成25年11月の生活保護法の改正法律案に対する付帯決議でも「いわゆる水際作戦はあってはならないことを、地方自治体に周知徹底すること」との決議がなされています。
生活保護事務は国(厚労省)から市町村等に委任されていますが実質が通知などにより監督しています。
上記の水際作成を否定する文言はその国から市町村等にされたものとなります。
本来の正常な保護開始までの手続きの順序は、次の通りとなります。
① 生活保護申請者に対して福祉事務所職員が必要な用紙を交付して申請者の質問がある場合は「面接相談」に応じ保護申請の援助をします。※面接相談は義務ではありませんが、丁寧に接してもらえる職員が面接を牙されるときはなるだけ協力してあげましょう。
⇩
② 保護申請者からの保護申請書その他の書類意を受領し調査を開始します。
⇩
③ 調査では、福祉事務所職員が、必要に応じて、
Ⅰ 訪問調査(自宅等住んでいるところに職員が行きます。)
Ⅱ 検診命令(指定の病院にて検診します。)
Ⅲ 金融機関等への照会(預金の状態を調査します。)
Ⅳ 扶養義務者の調査(親族等の存在を調査します。)
を行います。
⇩
④ 法律に規定する保護開始の要件を満たす場合は、保護開始の決定をして申請者に書面で通知します。要件を満たさないと判断をした場合は却下の決定を申請者に通知します。
⇩
⑤ 保護開始の決定のあった各種の扶助(※生活扶助や教育扶助など)の給付がなされます。
生活保護制度の利用の流れは次の通りとなります。
① 生活保護申請書その他の書面を福祉事務所長へ提出
(申請のできない急迫した状況の場合は職権による保護が必要)
⇩
② 郵送または持参による関係書類の到着後、調査や審査の開始(※郵送でも可能なことに注意)
⇩
③ 保護の要否の判定と申請者への14日(最大30日)以内の通知(※申請の握り潰しを制するため期間は法定されている)
⇩
④ 保護利用開始後の変化(※扶養義務者の扶養が決まる等)に伴う保護内容の変更(※保護費の減額)や指導指示
⇩
⑤ 保護の継続または保護の停止廃止
本来の正常な手続きでは、むしろ生活保護の申請をしようとする者の申請が速やかに行われるように福祉事務所職員は必要な援助を行わなければならないのです。
こういったことは福祉事務所職員も公務員である以上法令に従った行政の執行でありあたりまえのことであり不作為等は犯罪に抵触することもあります。
生活保護法施行規則1条2項でも、保護の実施期間は「保護の開始の申請について、申請者が申請する意思を表明しているときは、当該申請が速やかに行われるよう必要な援助を行わなければならない」と規定しているのです。
申請書用紙その他の必要な用紙の交付を拒否された場合は、「申請する意思」を明確に表明します。生活保護法に規定する保護開始の要件を満たすか否かは福祉事務所長の判断によるものであって、窓口の担当者の判断で保護の要否の決定をすることはできません。
保護の要否の決定(福祉事務所等による行政処分)の通知を受けなければ、保護開始の要件を満たしているのかどうかの判断ができませんし、仮に要件を満たしていない場合には、書面による通知によってその理由を知ることができますから、申請要件を満たした場合に再度の申請を行うこともできるのです。
(上記は、『水際作戦』と思われる場合にはとても有効です。但し真摯に向き合っていただける職員さんもいらっしゃいますのでそのときは協力しましょう。)
面接相談の強制と同行拒否
福祉事務所職員は、「面接相談」を受けないと申請書用紙その他の必要な用紙を交付しないとして面接相談を強制することはできません。しかし、申請をしようとする者の質問に対しては、福祉事務所職員は、申請関係書類の書き方その他の申請の仕方を教えるような申請を援助する義務があります。(生活保護法施行規則1条2項)
水際作戦の一つに「同行拒否」があります。初めて生活保護申請をする者には、福祉事務所の公務員の説明が正しいのか否かもわかりませんから生活保護法に詳しい支援者(弁護士、司法書士、行政書士)や市議会議員の同席を希望する場合が多いのですが、同行者の同席を認めない自治体が多数存在しました。公務員が同行拒否をする主な理由は、明らかに要保護状態にあるにもかかわらず、「保護の要件を満たしていないので仕事を探すように」とか「親族に援助をしてもらうように」といって申請をしたいものを追い返す水際作戦とって、同行者の同席は都合が悪いからです。
面接相談の強制や同行者の同行拒否という「水際作戦」によって生活保護申請をさせない場合には、なんとしても「生活保護申請書」を居住地の福祉事務所あてに郵送により提出する必要があります。
持参すると内容に不備あるとかその他の理由を付けて受け取り拒否をする場合がありますから、普通郵便又は書留郵便(郵便局職員が配達の記録を取る郵便)で郵送をします。
申請書が福祉事務所に到達した時点で申請の法的効果(申請受け取りを推定する)が発生し福祉事務所長に遅滞なく当該申請の審査を開始する義務が発生します(行政手続法7条)。
その申請書の記載事項に不備がある場合、申請書に必要に書類が添付されていない場合その他の不備があった場合は、福祉事務所長は、速やかに、申請をした者に対して相当の期間を定めて補正を求める必要があります(行政手続法7条)。
申請書を審査した結果、保護の要件を満たさないと判断した場合又は申請自体が不適法とは判断した場合は、福祉事務所長は、申請者に対して書面で却下(※上記の「不備」は住所の失念などミスが軽微な場合。「不適法」とは手持ちの資産等が多すぎる)の決定を通知します(生活保護法第24条3項)。
却下の決定に対しては不服申立(審査請求)できますが、不服申立をした場合でも、却下の理由を検討して再度の申請書を提出することが大切です。
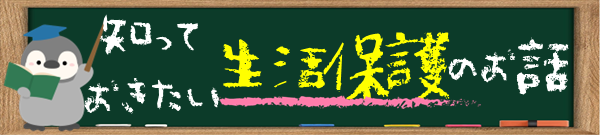
1-320x180.jpg)
2-320x180.jpg)
3-320x180.jpg)
4-320x180.jpg)
5-320x180.jpg)

2-160x90.jpg)