保護決定のための調査
生活保護申請書が福祉事務所等に到達すると必ず受領することになります。福祉事務所では、原則14日以内に申請者への通知が必要なため審査を始めなければなりません。
保護の決定等のため必要がある場合は、要保護者の資産や収入の状況、健康状態その他の事項を調査するために次のような調査等を実施します。
① 要保護者の居住場所への立ち入り調査(生活保護法第28条1項)
↓
② 要保護者への健診命令(健康診断)(生活保護法第28条1項)
↓
③ 要保護者への報告請求(主に資産状態、扶養義務者の存在等)(生活保護法第28条1項)
↓
④ 扶養義務者への照会(生活保護法第28条2項)
↓
⑤ 官公署その他の関係機関への照会(主に年金等の収入に関する調査)(生活保護法第29条)
上記の、
①立ち入り調査
②検診命令
③報告請求の調査等
に従わなかった場合には、福祉事務所長は、保護の申請を却下することができるとされています(生活保護法第28条5項)。
生活保護法第28条5項では、保護の実施機関(福祉事務所長)は、次の場合には保護の申請を却下することができるとしています。
実務では申請の際に
①「資産申告書」
②「収入申告書」
③「官公署等に対する調査に関する同意書」
は最初の申請の際に要求されることが多いです。
ア 上記①の要保護者の居住場所への立入調査を、要保護者が拒み、妨げ、又は忌避した場合
イ 上記②の検診命令については、要保護者が、医師または歯科医師の健診を受けるべき旨の命令に従わなかった場合
ウ 上記③の要保護者に対する報告は、要保護者が報告を求められたのに報告をせず、又は虚偽の報告をした場合
生活保護法第28条5項では、上記のアイウの場合には、福祉事務所長は、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができるとしています。
保護決定のための調査方法の内容
要保護者の居住場所への立ち入り調査の目的は、
① 要保護者の資産及び収入の状況
② 健康状態その他の事項を調査すること
にありますが、(生活保護法第28条1項)保護申請書に添付して提出する必要のある次の「資産申告書」や「収入申告書」は、所定の記入用紙の交付を受けて申請時に提出します(生活保護法第24条1項4号)。
※「資産申告書1」「資産申告書2」「収入申告書1」「収入申告書2」の例
A 資産申告書には、要保護者の世帯員の所有する
①土地・建物
②預金
③有価証券
④生命保険その他の保険
⑤自動車
⑥貴金属
⑦負債(借金)
について記載します。
B 収入申告書には、働いて得た
収入
年金・恩給
仕送りによる収入
その他の収入(ex.田畑を有していて野菜が取れる等)
将来見込まれる収入
を記載します。
立入調査に備えて可能な範囲で所持する次の書類等を準備しておくと便利です。
①預金通帳、生命保険・火災保険その他の保険証書
②年金手帳、年金証書、年金振込通知葉書
③土地・建物の権利証、土地・建物の賃貸借契約書
④最近3カ月の給与明細書
⑤健康保険被保険者証その他の医療保険加入者証、介護保険被保険者証
⑥電機、ガス、水道、電話の最近の領収書または請求書
⑦身体障碍者手帳
⑧保護申請書に押印した印鑑(訂正用の認め印)
要保護者への検診命令については、福祉事務所長は、健康状態その他の事項を調査するために福祉事務所長の指定する医師または歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができます。(生活保護法第28条1項)。
保護開始の申請時点で検診命令がなされる場合には、例えば、
①稼働能力(働ける能力)の有無に疑いがある場合(※うつ病やパニック障害などの精神疾患がある場合も稼働能力がないとされる。)
②障碍者加算(障碍者認定を受ける者はプラスしてもらえることがある)の認定に必要と認める場合
③医療扶助(医者にかかるための費用)の決定に際して要保護者の病状に疑いがある場合
④介護扶助(介護にかかるための費用)の決定に際して医学的判断が必要な場合
があります。
検診命令は福祉事務所長の命令で行うものですから、保護申請者の費用負担はありません。
福祉事務所長は、生活保護申請書の到達前に申請をしようとする者に対して検診を命じたり診断書の提出を命ずることはできません。(あくまで保護申請の審査が開始されてから検診に行くことになる。)
要保護者への報告請求については、福祉事務所長は、要保護者の資産や収入の状況、健康状態その他の事項について、要保護者に対して報告を求めることができます(生活保護法第28条1項)。
この報告請求に対して、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、福祉事務所長は、保護開始の申請を却下することができるとしています。(生活保護法第28条5項)
扶養義務者等(両親や未成年の子等)への照会については、福祉事務所長は、保護の開始決定その他の必要があると認める場合は、保護開始の申請書や添付書類の内容を調査するために要保護者の扶養義務者その他の同居の親族等に対して報告を求めることができるとしています。(生活保護法第28条2項)。
更に、
生活保護法第24条8項
保護の実施期間は、知れたる扶養義務者が民法の規定による決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもって厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合はこの限りでない。
と規定しています。
例えば、夫の暴力から逃れて隠れている妻の保護開始申請に際して夫に紹介するのは適当でないので、このよう場合は、申請時点で照会をしないように福祉事務所長に報告しておく必要があります。
官公署その他の関係機関への照会については、福祉事務所長や保護の実施機関(市長や知事)は、保護の開始決定その他の必要があると認める場合は、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構、共済組合等に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に報告を求めることができます。(生活保護法第29条1項)
① 要保護者又は被保護者であった者
氏名及び住所又は居所
資産および収入の状況
健康状態
他の保護の実施機関における保護の決定及びその他政令で定める事項
② 上記①の者の扶養義務者
氏名及び住所又は居所
資産及び収入の状況その他政令で定める事項
※ 注意すべきは扶養義務者に通知することは原則拒めませんが、扶養義務者が扶養の通知を受領し資産があるにも関わらず扶養を拒否した場合でもそれが理由で生活保護申請は却下されることはありません。
なお、民間事業者に回答を強制することはできませんが、生活保護法第29条2項では、官公署の長、日本年金機構、共済組合等の公的団体には「書類を閲覧させ、又は資料の提供を行うものとする」と規定しています。
紹介先が民間事業者の場合は、個人情報の保護のため本人の同意なしに回答することはできませんから、福祉事務所では、申請者に対して包括的な同意書の提出を求めています。
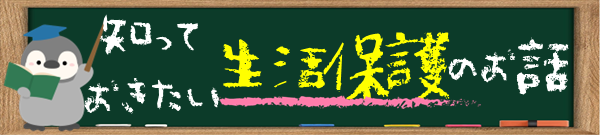
1-320x180.jpg)
2-320x180.jpg)
3-320x180.jpg)
4-320x180.jpg)
5-320x180.jpg)

2-160x90.jpg)