主産扶助とは
出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、次に掲げる事項の範囲何において行われます(生活保護法第16条)。
①分べんの介助
②分べん前又は分べん後の処置
③脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料
通常の分べん(出産)は、病気の治療には該当しませんから医療扶助の対象とはなりませんが、出産費用は高額になることから、これを保護対象としたものです。分べんには、出産その他死産や流産も含まれますが、人工中絶の場合は医療扶助の対象となります。
出産扶助の内容
出産扶助の対象は、①分べんの介助、②分べん前の又は分べん後の処置、③脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料とされていますが、病院、助産所等の施設において分べんをする場合は、入院(8日以内の実入院日数)に要する必要最小限度の額が基準額に加算されます。
出産扶助の方法は次の通りとなります(生活保護法第35条)。
① 出産扶助は、
法律上原則「金銭給付」
によって行います。
ただし、例外として、
(a)これによることができない場合
(b)これによることが適当でない場合
(c)その他保護の目的を達するために必要がある場合
は、法律上例外的に「現物給付」によって行うことができます。
※実務上では現物給付がほとんどのようです。
② 出産扶助の現物給付のうち、出産扶助の給付は、知事の指定を受けた助産師に委託して行うものとしています。
③ 急迫した事情その他やむを得ない事情がある場合には、被保護者は、指定を受けない助産師の出産の給付を受けることができます。
④ 出産扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付されます。
出産扶助の一般基準は、次の通りになっています。
別表第6 出産扶助基準
| 区分 | 基準額 |
| 出産に要する費用 | 311,000円以内 |
※ 難産などで費用が増加する場合でも医療扶助として別のカテゴリーでカバーされる。
病院や助産所のような施設で分べんをする場合は、入院に要する必要最小限度の額が上記の基準額に加算されます。衛生材料を必要とする場合は5,700円の範囲内で上記の基準額に加算されます。
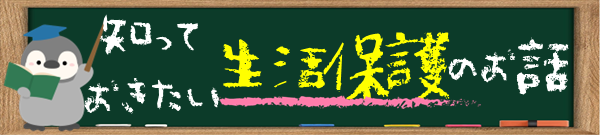
1-320x180.jpg)
2-320x180.jpg)
3-320x180.jpg)
4-320x180.jpg)
5-320x180.jpg)

3-160x90.jpg)