保護施設の種類
生活保護の保護施設には、次の5種類の施設があります(生活保護法第38条1項)。
① 救護施設
② 更生施設
③ 医療保護施設
④ 授産施設
⑤ 宿所提供施設
各保護施設の内容は次の通りです(生活保護法第38条2項~6項)。
① 救護施設とは、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設
② 更生施設とは、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設
③ 医療保護施設とは、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設
④ 授産施設とは、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設
⑤ 宿所提供施設とは、住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設
保護施設の基準と設置
都道府県は、保護施設の設備や運営について条例で基準を定める必要があります。その条例には、次の①②③については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項についてはその省令基準を参酌することとしています。(生活保護法第39条)
① 保護施設に配置する職員とその員数
② 保護施設にかかる居室の床面積
③ 保護施設の運営に関する事項で利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
④保護施設の利用定員
保護施設を設置することができるのは、
①都道府県
②市区町村
③地方独立行政法人
④社会福祉法人
⑤日本赤十字社
に限られます(生活保護法第41条1項)。
保護施設を設置する場合には、その施設に配置する職員数、施設の居室の床面積その他の事項について厚生労働省令に規定する基準を満たす必要があります。
都道府県知事は、保護施設の運営について必要な指導をする必要があります。ただ、社会福祉法人又は日本赤十字社の設置した保護施設に対する指導については、市町村長が、これを補助することとしています。(生活保護法第43条)
都道府県知事は、保護施設の管理者に対して、その業務若しくは会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は都道府県職員に、その施設に立ち入り会計書類その他の書類を検査させることができます。(生活保護法第44条)。
保護施設の義務
保護施設の義務として次の義務があります(生活保護法第47条)。
① 保護施設は、保護の実施機関から保護のための委託を受けた場合は、正当な理由なくして、これを拒否してはなりません。
② 保護施設は、要保護者の入所又は処遇に当たり、人種、信条、社会的身分又は門地により差別的または優先的な取り扱いをしてはなりません。
③ 保護施設は、これを利用する者に対して、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制してはなりません。
④ 保護施設は、都道府県職員による立ち入り検査を拒んではなりません。。
保護施設の長は、常に、その施設を利用する者の生活の向上及び更生を図ることに努める必要があります。
保護施設の長は、その施設を利用する者に対して、管理規程に従って必要な指導をすることができますが、都道府県知事は、必要と認める場合は、その指導を制限し又は禁止することができます。
保護施設の長は、その施設を利用する被保護者について、保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認める場合は、速やかに保護の実施機関に届け出る必要があります(生活保護法第48条)
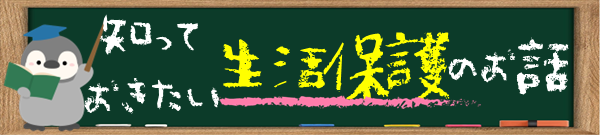
1-320x180.jpg)
2-320x180.jpg)
3-320x180.jpg)
4-320x180.jpg)
5-320x180.jpg)

5-160x90.jpg)