収入に関する申告と調査の実務
要保護者が保護の開始または変更の申請をした場合のほか、次のような場合に要保護者の収入に関し申告を行わせることとしています。
① 保護の実施機関において収入に関する定期または随時の認定を行うとする場合
② その世帯の収入に変動があったことが推定され又は変動のあることが予想される場合
収入に変動がある場合の申告については、あらかじめ被保護者に申告の要領、手続き等を十分理解させ、つとめて自主的な申告を敢行させることとしています。
収入に関する申告は、
・収入を得る関係先
・収入を得る関係先
・収入の有無
・程度
・内訳等
について行わせるものとし、保護の目的達成に必要な場合においては、その申告を書面で行わせることとしています。この場合にこれらの事項を証明すべき資料があれば、必ずそれを提出させることとしています。
収入の認定に当たっては、上記によるほか、
・その世帯の預金
・現金
・動産
・不動産等の資産の状況
・世帯員の生活歴
・技能
・稼働能力等の状況
・社会保険その他社会保障的施策による受給資格の有無
・扶養義務者又は縁故者等からの援助
・その世帯における金銭収入等
のすべてについて綿密な調査を行い、必要に応じて関係先につき調査を行う等収入源について直接に把握することとしています。
収入額の認定の原則
収入減の認定は、月額によることとし、この場合において、
・収入がほぼ確実に推定できる場合は、その額により
・そうでない場合は、前3カ月間程度における収入額を標準として定めた額により
・数カ月若しくはそれ以上の長期間にわたって収入の実情につき観察することを適当とする場合は、長期間の観察の結果により
それぞれ適正認定することとしています。
勤労(被用)収入については、官公署、会社、工場、商店等に常用で勤務し、又は日雇いその他により勤労収入を得ているものでは、基本給、勤務地手当、家族手当及び超過勤務手当等収入総額を認定することとしています。
この場合の勤労収入を得るための必要経費としては、
・通勤費(電車・バス・自転車・自動車など、通勤に必要な費用)
・職業用道具、用品(作業服、作業靴、安全帽、工具、器具など)
・職務上の消耗品(消耗品、作業中に使用する備品)
・資格取得・研修費(就労に必要な資格取得や研修費用)
・通信費(業務に必要な電話・インターネット費)
・社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険の本人負担分)
・職場に必要な制服クリーニング費(制服や作業服のクリーニング費用)
・車両維持費(業務使用分)(自動車・バイクの維持費(燃料・保険・駐車場)※通勤や仕事で直接使用する場合に限る)
・資格更新費用(必要資格の更新や登録料)
・研修参加交通費・宿泊費(研修参加に必要な交通費・宿泊費)
の実費の額を認定することとしています。
農業収入については、農業により収入を得ているものでは、すべての農作物につき調査をし、その収穫量に基づいて認定することとしています。
農業収入を得るための必要経費としては、基礎控除額表によるほか、生産必要経費として
・小作料
・農業災害補償法による掛金
・雇人費
・農機具の修理費
・少額農具の購入費
・納屋の修理費
・水利組合費
・肥料代
・種苗代
・薬剤費等についてその実際必要額
を認定することとしています。
農業以外の事業(自営)収入については、農業以外の事業(固定的な内職を含む)により収入を得ている者では、その事業の種類に応じて、実際の収入額を認定し、又はその地域の同業者の収入の状況、その世帯の日常生活の状況等から客観的根拠に基づいた妥当性のある認定を行うこととしています。
この場合の必要経費については、
・その事業に必要な経費として店舗の家賃
・地代
・機械器具の修理費
・店舗の修理費
・原材料費
・仕入代
・交通費
・運搬費等の諸経費
についてその実際必要額を認定することとしています。
ただし、家賃、地代等の額に住宅費を含めて処理する場合には住宅費にこれらの費用を重ねて計上しないこととしているほか、下宿間貸業で家屋が自己の所有でなく家賃を必要とする場合は、下宿間貸代の範囲内において実際家賃を認定して差し支えないとしています。
不安定な就労による収入(知人・近隣等寄りの臨時的な報酬の性質を有する少額の金銭その他少額かつ不安定な稼働収入)については、その額(受領するために交通費を要した場合はその必要経費を控除した額)が、月額15,000円を超える場合は、その超える額を収入として認定することとしています。
年金、恩給、失業保険金その他の公の給付(自治体又はその長が条例又は予算措置により定期的に支出する金銭を含む)については、その実際の受給額を認定することとしています。
ただし、次に該当する額については除かれます。
①災害等で損害を受けたことによる保証金等で自立更生に当たられる額
②社会的障碍者に自治体が定期に支給する自治体から支給される年金
③心身障害者扶養共済制度により自治体から支給される年金
年金・恩給等の収入を得るために必要な経費として
・交通費
・所得税
・郵便料
・受給資格証明のために必要とした費用
を要する場合その実際必要額を認定するととしています。
仕送り、贈与等による収入ついては、社会通念上収入として認定することを適当としないもの(例えば、葬儀の際の香典)のほかは、すべて認定することとしています。
仕送り、贈与等による主食・野菜・魚介は、その量について農業収入または農業以外の認定の例により金銭に換算した額を認定することとしています。
これらの収入を得るために必要な経費として、
・これを受領するための交通費等
を必要とする場合は、その実際必要額を認定することとしています。
財産収入(田畑、家屋、機械器具等を他に利用させて得られる地代、小作料、家賃、間代、使用料等の収入)については、その実際の収入額を認定することとしています。家屋の補修費、地代、機械器具等の修理費、その他財産収入を上げるために必要とする経費については、最小限度の額を認定することとしています。
不動産又は動産の処分による収入、保険金その他の臨時的収入については、その額(受領するための必要経費を控除した額)が世帯合算月額8,000円を超える場合は、その超える額を収入として認定することとしています。
収入として認定しない例は次の通りです。
① 社会事業団体その他(自治体とその長を除く)から被保護者に対して臨時的に恵与去られた慈善的性質を有する金銭であって、社会通念上収入として認定することが適当でないもの
② 出産、就職、結婚、葬祭等に際して贈与にされる金銭であって、社会通念上収入として認定することが適当でないもの
③ 自立更生を目的として恵与される金銭のうち被保護世帯の自立支援更生のためにあてられる額
④ 災害等によって損害を受けたことにより臨時的に受ける補償金、保険金又は見舞金のうち被保護世帯の自立更生のためにあてられる額
⑤ 死亡を支給自由として臨時的に受ける保険金のうち被保護世帯の自立更生のためにあてられる額
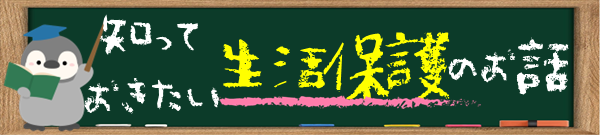
1-320x180.jpg)
2-320x180.jpg)
3-320x180.jpg)
4-320x180.jpg)
5-320x180.jpg)

4-160x90.jpg)